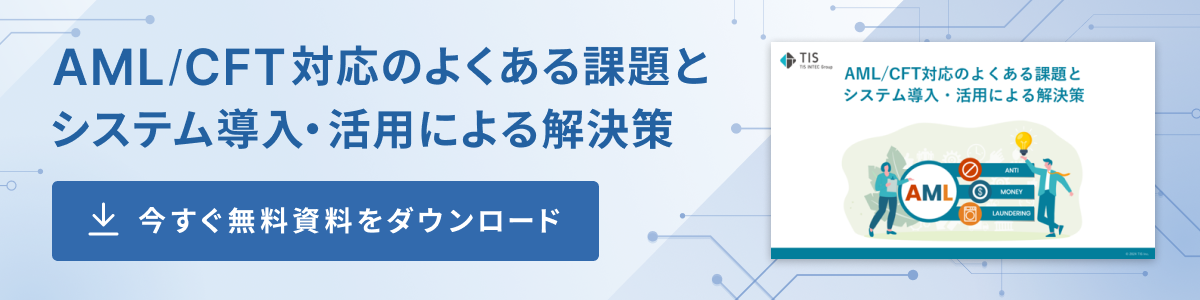マネーローンダリング対策(AML:Anti-Money Laundering)は、金融・決済サービスの事業者が果たすべき重要な義務の一つです。
マネーローンダリング対策は世界的に行われている取り組みであり、日本でも法律やガイドラインの整備が進んでいます。マネーローンダリング防止のために、具体的にどのような対策が求められているかを理解するには、実際の事例や各業界での対策を把握することが重要です。
本ページでは、マネーローンダリングの定義や具体的な事例、対策方法について詳しく解説します。
1 マネーローンダリングとは?
2 マネーローンダリングの手口
2-1 プレイスメント
2-2 レイヤリング
2-3 インテグレーション
3 マネーローンダリングにあたる行為はどのようなもの?
3-1 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為(第9条)
3-2 犯罪収益等隠匿(第10条)
3-3 犯罪収益等収受(第11条)
4 マネーローンダリングの具体事例
4-1 電子マネーを利用した事例
4-2 暗号資産を利用した事例
4-3 他人名義の銀行口座を利用した事例
5 マネーローンダリングの対策方法
5-1 銀行の対策
5-2 保険会社の対策
5-3 証券会社の対策
5-4 暗号資産取引業者の対策
5-5 クレジットカード事業者の対策
5-6 不動産業者の対策
6 まとめ
1 マネーローンダリングとは?
マネーローンダリング(Money Laundering)とは、犯罪によって得た収益を、正当な手段で得たかのように偽装する「資金洗浄」のことです。
警察などの捜査機関では、資金の流れを追跡することで犯罪捜査を進めることがあります。マネーローンダリングは、こうした捜査機関の追跡を逃れる行為の一つです。
自社のサービスを利用してマネーローンダリングが行われることを放置すると、犯罪を助長するリスクがあり、社会的な信用を損なう可能性があります。
世界ではFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)がマネーローンダリング防止の基本方針を策定しており、日本国内でも金融庁がガイドラインを整備し、対策を強化しています。
金融・決済サービスなど、マネーローンダリングに悪用される可能性がある事業を行う企業は、こうした世界的な対策強化の流れに適切に対応することが求められます。
2 マネーローンダリングの手口
マネーローンダリングは、以下の3つのステップで行われるとされています。
- プレイスメント
- レイヤリング
- インテグレーション
それぞれの手口について、具体的に解説します。
2-1 プレイスメント
プレイスメントとは、犯罪によって得た収益を金融システムや商取引などに「組み込む」ことです。例えば、以下のような方法で、収益を別の形に置き換えます。
- 銀行口座への入金
- 不動産の購入
- 株の購入
- 暗号資産の購入
プレイスメントの際には、他人の名義を使用するなどして、犯罪とは無関係の取引であるかのように偽装することが一般的です。
また、大口の入金が不審に思われるのを避けるため、小口に分けて入金を行う「ストラクチャリング」と呼ばれる手法が使われることがあります。
2-2 レイヤリング
インテグレーションとは、資金を健全な経済に「統合」させるプロセスです。犯罪によって得た収益を「回収する段階」を指します。
例えば、犯罪の収益で購入した不動産を売却して代金を得たり、購入した暗号資産を現金化したりといった手口のことです。
不動産等の資金をそのまま売却すると資金の出所が明らかになるため、通常は前述の「レイヤリング」を経て、経路が分からないよう偽装した上で売却されます。
2-3 インテグレーション
インテグレーションとは、資金を健全な経済に「統合」させるプロセスです。犯罪によって得た収益を「回収する段階」を指します。
例えば、犯罪の収益で購入した不動産を売却して代金を得たり、購入した暗号資産を現金化したりといった手口のことです。
不動産等の資金をそのまま売却すると資金の出所が明らかになるため、通常は前述の「レイヤリング」を経て、経路が分からないよう偽装した上で売却されます。
3 マネーローンダリングにあたる行為はどのようなもの?
マネーローンダリングは、その行為自体が犯罪です。「組織的犯罪処罰法」に違反する行為として、以下の3つが規定されています。
- 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為(第9条)
- 犯罪収益等隠匿(第10条)
- 犯罪収益等収受(第11条)
出典:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
それぞれの行為について、詳しく見ていきましょう。
3-1 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為(第9条)
これは、犯罪によって得た収益を利用して株を取得するなどして、法人の経営に影響を与える権利を取得し、それを行使する行為を指します。例えば、役員を変更させるなどして経営に影響を与えることが該当します。
3-2 犯罪収益等隠匿(第10条)
これは、犯罪によって得た収益の存在を隠したり、処分した事実を隠ぺいする行為を指します。また、収益の出所を隠す行為も「犯罪収益等隠匿」に該当します。さらに、隠ぺいが未遂に終わった場合や、隠ぺいを準備した段階(予備罪)でも、処罰の対象になります。
3-3 犯罪収益等収受(第11条)
これは、犯罪によって得た収益と知りながら、それを受け取る行為を指します。
ただし、以下2つのケースは例外として条文で規定されています。
- 法令上の「義務の履行」として犯罪収益を受け取った場合
- 犯罪が関係していることを知らずに締結した契約の債務の履行として犯罪収益を受け取った場合
4 マネーローンダリングの具体事例
実際に発生したマネーローンダリングの事例を見ていきましょう。令和2年~令和4年に発生した事例では、マネーローンダリングに利用された取引の種類が多岐にわたっています。現金・預金取引に加え、「クレジットカード」や「前払式支払手段(電子マネー)」など、キャッシュレス決済を悪用した事例も多く報告されています。
| 悪用された取引 | 合計(件) |
|---|---|
| 内国為替取引 | 584 |
| 現金取引 | 297 |
| 預金取引 | 160 |
| クレジットカード | 115 |
| 前払式支払手段(※) | 71 |
| 暗号資産 | 57 |
| 法人格 | 36 |
| 外国との取引(外国為替等) | 32 |
| 資金移動サービス | 20 |
| 宝石・貴金属 | 5 |
| 法律・会計専門家 | 3 |
| 外貨両替 | 2 |
| 金融商品 | 2 |
※令和5年犯罪収益移転危険度調査書から、電子マネーの名称を前払式支払手段に変更。令和2年及び3年の前払式支払手段の数値は、電子マネーのうち前払式支払手段に該当した取引を計上
出典:国家公安委員会『犯罪収益移転危険度調査書』P30図表 12より抜粋
以下では、警察庁の『犯罪収益移転防止に関する年次報告書』で公開されている事例から、8つのケースをピックアップして紹介します。
4-1 電子マネーを利用した事例
特殊詐欺グループが被害者からだまし取ったキャッシュカードを使用し、会社員の男性がATMから出金。その現金で電子マネーを購入し、コード番号をメッセージアプリで送信した。(令和5年1月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)』P45【事例1】
会社員の男性が他人になりすまして自動車を販売。なりすました人物による正当な収益であるかのように偽装し、販売代金の受け取りには電子マネーが使用された。(令和5年6月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)』P45【事例2】を参照
4-2 暗号資産を利用した事例
ベトナム人の男性数人が、日本からベトナムへの送金希望者から資金をだまし取り、受け取った金額の一部を不正に開設した暗号資産口座に入金。その後、日本国内の暗号資産交換業者を通じて暗号資産に換金し、さらに海外の暗号資産交換業者を通じてベトナム現地通貨に換金した。(令和5年6月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)』P47【事例10】
コンサルタント業の男性らが、特殊詐欺グループがだまし取った電子マネーを取得。他人が経営する合同会社の名義を使用し、なりすまして売却した。(令和4年4月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)』P43【事例2】
会社員の男性が、自分の銀行口座に入金された犯罪収益で暗号資産を購入。その後、管理者不明の暗号資産アドレスに移転した。(令和4年2月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)』P43【事例3】
4-3 他人名義の銀行口座を利用した事例
ベトナム人の男性がインターネットを利用した詐欺を行い、被害者名義の口座から他人名義の口座に預金を振込送金させた。(令和5年6月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)』P46【事例8】
特殊詐欺グループが被害者に指示し、被害金をさらに別の他人名義の口座に入金させた。さらに、別の男性に指示を出し、被害金をさらに別の他人名義の口座へ移転させる手口が発覚。(令和4年1月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)』P43【事例1】
会社役員の男性が、詐欺によって得た収益をガーナ共和国の銀行口座に送金。その際、カカオ豆などの購入代金の請求書を偽造し、正当な商取引であるかのように装った。(令和4年2月の事例)
出典: 警察庁『犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和5年)』P45【事例10】
5 マネーローンダリングの対策方法
マネーローンダリングを防止するため、各業界ではさまざまな取り組みが行われています。一部の対策は法律で義務化されており、共通する部分もありますが、業界ごとに異なる対応が求められます。ここでは、以下の6つの業種における主な対策を紹介します。
- 銀行
- 保険会社
- 証券会社
- 暗号資産取引業者
- クレジットカード事業
- 不動産業者
5-1 銀行の対策
銀行では、口座を保有する利用者に対し、「お客さま情報ご提供のお願い」や「お取引目的等確認書」などの書類を郵送し、利用者情報を最新の状態に保つ取り組みを行っています。これはFATFが求める国際基準に沿ったものであり、銀行だけではなく金融業界全体で推進されています。
出典: 金融機関からの「お客さま情報」や「お取引目的」の確認にご協力ください! | 政府広報オンライン
5-2 保険会社の対策
保険会社では、マネーローンダリングなどを防止のため、貯蓄性の高い保険や200万円を越える大口取引の確認記録・取引記録の作成・保存や、マネーローンダリングやテロ資金供与の可能性がある「疑わしい取引」の金融庁への届出が義務付けられています。
出典: マネーローンダリング/テロ資金供与対策 Q&A|一般社団法人生命保険協会
5-3 証券会社の対策
証券会社では、銀行や保険会社と同様に、利用者情報の最新化や疑わしい取引の届出が行われています。また、日本証券業協会は、マネーローンダリングやテロ資金供与対策の啓発活動として、店頭掲示用のポスターや配付用のリーフレットを各証券会社へ提供し、利用者への理解を図っています。
出典: 証券業界におけるマネーローンダリング及びテロ資金供与対策への取組み | 日本証券業協会
5-4 暗号資産取引業者の対策
暗号資産取引業界では、マネーローンダリングやテロ資金供与防止のため「トラベルルール」と呼ばれる対策が導入されています。
トラベルルールとは、利用者が暗号資産を送付する際に、依頼人と受取人の情報を、受取人側の暗号資産交換業者に通知する義務を課すルールです。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において、「暗号資産の移転に係る通知義務」として規定されており、FATFが求める国際基準にも準拠しています。
5-5 クレジットカード事業者の対策
クレジットカード業界では、経済産業省が作成したガイドラインに基づき、疑わしい取引を検知するためのITシステムの導入や、取引のモニタリング・フィルタリング体制の構築などの対策が行われています。ガイドラインに記載されている内容以外に、業界団体等より共有される事例や当局等からの情報等を参照し、自らのリスクに見合った低減措置を工夫することが求められています。
出典: 経済産業省|クレジットカード業におけるマネーローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
5-6 不動産業者の対策
不動産業者(宅地建物取引業者)は、マネーローンダリング対策を行うべき「特定事業者」として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく義務を負っています。例えば、疑わしい取引の届出(銀行や保険会社と同様)、「犯罪収益移転防止等連絡協議会」を設置、不動産業界の各団体に向けて、マネーローンダリング対策の啓発活動を行っています。
出典: 不動産業におけるマネーローンダリング対策(犯罪収益移転防止法)の推進 | お知らせ | 全宅連
6 まとめ
金融・決済サービス事業者にとってマネーローンダリング対策(AML)は、テロ資金供与対策(CFT)と併せて取り組むべき重要な課題です。
AML/CFTを適切に実施するには、取引モニタリング・フィルタリングが可能なシステム導入、適切な対応ができる人材の確保、AML/CFT対策を適切に運用するための社内体制の構築も必要です。
TISでは、AML/CFTに対応するためのシステム導入を統合的に提供する「AML/CFT統合サービス」をご用意しています。AML/CFT業務のコンサルティングや、業務代行(BPO)にも対応可能です。詳しいサービス内容は、以下のページをご確認ください。
AML/CFT統合サービス | PAYCIERGE(ペイシェルジュ)
【AML/CFT関連記事はこちら】
●マネー・ローンダリング対策とは?銀行などの金融機関が取り組むべき施策も解説
●金融庁のマネロン対策ガイドラインを解説!最新の改正ポイントとリスク軽減のための対応とは
●CFTとは?金融犯罪におけるCFTの重要性や取り組み事例について解説
※この記事が参考になった!面白かった! と思った方は是非「シェア」ボタンを押してください。