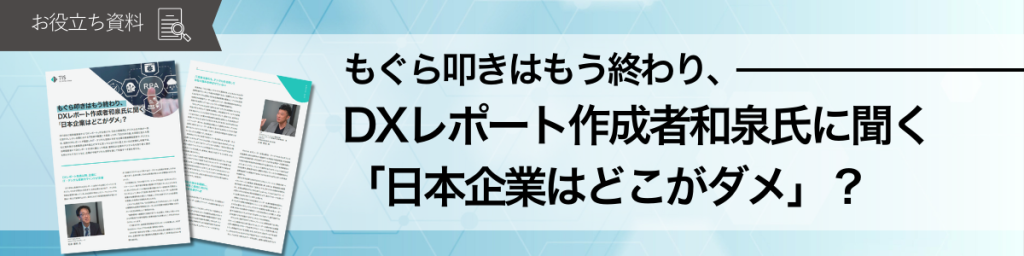サプライチェーンを適切に管理する「サプライチェーンマネジメント」において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が高まっています。DXを推進するには、適切なテクノロジーの導入が不可欠ですが、具体的にどのようなテクノロジーやツールを活用すれば、サプライチェーンのDXを実現できるのでしょうか。
本コラムでは、サプライチェーンマネジメントにおけるDXの基本概念と、導入を検討すべきテクノロジーや具体的なツール・サービスについて、詳しくご紹介します。
1 サプライチェーンにおけるDXとは
1-1 デジタル化との違い
2 サプライチェーンマネジメントにおけるDXの必要性
2-1 レガシーシステムの問題に対応するため
2-2 人材不足に対応するため
2-3 企業の競争力を高めるため
3 サプライチェーンのDXに向けて検討したい施策
3-1 一部業務のアウトソーシング
3-2 情報を共有するネットワークの構築
3-3 タスクの自動化
3-4 チャネルの拡大
4 サプライチェーンのDXで導入を検討したいテクノロジー
4-1 IoT(モノのインターネット)
4-2 AI(人工知能)・ビッグデータ
4-3 クラウドサービス
5 サプライチェーンのDXに役立つツール・サービスの具体例
5-1 ERPシステム
5-2 RPAツール
5-3 BPSP
6 サプライチェーンのDXはデジタル化から始める
1 サプライチェーンにおけるDXとは
サプライチェーンにおけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を活用してサプライチェーンマネジメントを変革し、競争力を向上させる取り組みです。DXは、単なる業務プロセスの改善にとどまらず、新しいビジネスモデルの創出や企業風土の改革など、大きな変革を目指すものです。そのため、単にデジタル技術を導入するだけでなく、組織全体の改革が求められます。
特に、AI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)・クラウドなどの先進的な技術を活用することで、より効果的で柔軟性のあるサプライチェーンを構築し、DXを推進することが可能になります。
1-1 デジタル化との違い
DXと混同されやすい言葉に「デジタル化」があります。デジタル化とは、従来アナログで行っていた業務をデジタル技術に置き換えることです。例えば、サプライチェーンにおいて紙の請求書を廃止し、Web上で請求業務を完結させることはデジタル化の一例です。
一方で、DXは単にデジタル化にとどまらず、業務の抜本的な改革や新たな価値創出を目指すものです。つまり、デジタル化はDXの一部に過ぎず、デジタル化を進めるだけではDXを実現することは難しいといえます。
2 サプライチェーンマネジメントにおけるDXの必要性
サプライチェーンの管理・最適化を目指す「サプライチェーンマネジメント」において、DXはなぜ必要なのでしょうか。主な理由として以下の3つが挙げられます。
- レガシーシステムの問題に対応するため
- 人材不足に対応するため
- 企業の競争力を高めるため
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
2-1 レガシーシステムの問題に対応するため
サプライチェーンマネジメントにDXが必要な理由の1つは、「レガシーシステム」の問題に対応するためです。レガシーシステムとは、過去の技術で構築され、現在も新しい技術に置き換えられずに運用されているシステムを指します。レガシーシステムは、長年にわたり更新・カスタマイズを繰り返して複雑化し、保守・管理の負担が増大している傾向にあります。レガシーシステムの運用を続けることは、保守・管理コストの増加につながり、サプライチェーンの効率化を阻害する要因になる可能性があります。
DXを推進し、レガシーシステムからの脱却を目指すことで、サプライチェーンマネジメントの全体最適化が実現されるでしょう。
2-2 人材不足に対応するため
人材不足の問題も、サプライチェーンマネジメントにDXが必要な理由の一つです。日本では少子高齢化の影響で労働人口が減少しており、製造・物流の現場においても人材不足が深刻化しています。DXにより、業務を自動化・効率化することで、少ない人員でも対応できるようになります。その結果、採用コストを削減できるだけでなく、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境が整い、個々のパフォーマンス向上にもつながり、企業全体の生産性が向上します。
2-3 企業の競争力を高めるため
サプライチェーンマネジメントのDXは、企業の競争力向上にもつながります。DXにより、企業のサプライチェーンがより柔軟で効率的になり、市場の変化に迅速に対応できるようになります。例えばサプライチェーン全体のデータをリアルタイムで分析することが容易になり、顧客ニーズの変化などに対して素早く対応できるようになります。DXによるデータ分析に基づく迅速な意思決定が可能となり、変化の激しい市場環境においても競争優位性を維持しやすい体制が整います。
3 サプライチェーンのDXに向けて検討したい施策
サプライチェーンのDXを実現するためには、具体的にどのような施策を行えば良いのでしょうか。取り組みやすい施策として以下の4つが挙げられます。
- 一部業務のアウトソーシング
- 情報を共有するネットワークの構築
- タスクの自動化
- チャネルの拡大
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 一部業務のアウトソーシング
サプライチェーンマネジメントの一部業務を「外部企業に委託」することは、DXを推進するうえで有効な施策の一つです。DXのために高性能なITシステムを一から構築するには、初期投資が大きく、運用コストやリスクも高くなるため、現実的でない場合があります。
近年ではDXに役立つさまざまなITツールやWebサービスが手軽に利用できるようになっており、既存の外部サービスを利用する方が効率的なケースも増えています。外部サービスの利用には費用が発生しますが、自社でシステムを開発・運用するよりも、コスト削減につながる可能性もあります。
3-2 情報を共有するネットワークの構築
サプライチェーンのDXを実現するためには、リアルタイムで情報を共有できる「ネットワークの構築」が不可欠です。製造・物流・販売・購買の情報が共有されるネットワークを構築することで、ニーズの変化や在庫状況などをリアルタイムで把握できます。蓄積されたデータをAIで分析してサプライチェーン全体の最適化を図ることも可能となり、サプライチェーン全体の変革が容易になります。
3-3 タスクの自動化
サプライチェーンマネジメントの中で、特定のタスクを「自動化」することもDX推進において重要な施策です。人手がかかるタスクを自動化することで、コスト削減や業務効率の向上、人的ミスの防止などが期待できます。例えば受発注やデータ入力などの定型業務は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用して自動化できます。また、生成AIを含むAI技術を導入することで、市場予測やデータ分析などの業務も効率化できるようになります。新しいテクノロジーを積極的に取り入れ、人が行う作業をできるだけ減らすことがDXの基本です。
3-4 チャネルの拡大
DXの本質は、既存のビジネス構造の「変革」にあります。その一環として「チャネルの拡大」は、サプライチェーンDXにおいて重要な施策の一つです。例えば、ECサイトの開設やマーケットプレイスへの出店、新たなマーケティング施策の導入など、これまで着手していないチャネルに挑戦できないか検討してみましょう。
各チャネルをそれぞれ個別に管理するのではなく、デジタルプラットフォームなどを活用して一元管理する方法も同時に検討する必要があります。特にオンラインとオフラインを連携させるオムニチャネル戦略を採用することで、より効果的なサプライチェーンDXを実現できます。チャネルを拡大し、それらをシームレスに連携することで、サプライチェーンのDXを加速させることができます。
4 サプライチェーンのDXで導入を検討したいテクノロジー
サプライチェーンのDXを実現するために、具体的にどのようなテクノロジーを導入すべきなのでしょうか。代表的なものとして以下の3つが挙げられます。
- IoT(モノのインターネット)
- AI(人工知能)・ビッグデータ
- クラウドサービス
それぞれDXにどのように貢献できるのか、以下に解説していきます。
4-1 IoT(モノのインターネット)
IoTは、特に物流や在庫管理などの分野で導入が期待されるテクノロジーです。
IoTとは「Internet of Things:モノのインターネット」の略で、建物・家具・乗り物などさまざまな”モノ”をインターネットに接続し、データを取得・活用する技術を指します。例えば物流・在庫管理におけるセンサー技術や自動監視などにIoTを導入することで、センサーやカメラで取得したデータをサプライチェーン全体にインターネットで共有することが可能です。共有したデータは、トラブルの早期発見や、データに基づいた供給の最適化などに活用されます。
4-2 AI(人工知能)・ビッグデータ
AIやビッグデータはサプライチェーンマネジメントのさまざまな分野に役立ちます。例えばAIを使って需要予測や生産計画を行うことで、在庫管理・商品配置の最適化を図れます。AIの画像解析では自動探知を、不良品判定などに導入することが可能です。また従業員の動きをAIで分析して倉庫内の最適なレイアウトを検討するなど、サプライチェーンの最適化を目指すためのさまざまな分析に、AIを活用できます。
4-3 クラウドサービス
クラウドサービスも、サプライチェーンDXを進めるうえで導入を検討すべきソリューションの一つです。
クラウドサービスとは、高度なソフトウェアやプラットフォーム、インフラなどをインターネット経由で利用できるITサービスです。クラウドサービスはインターネット上に接続すれば利用できるため、社内にサーバーを設置するなどのインフラ構築が不要で、導入コストを抑えられるというメリットがあります。またインターネット経由でどこからでも同じデータ・環境にアクセスできることもメリットで、リアルタイムでの情報共有にも役立ちます。クラウドサービスを活用し、サプライチェーン全体のデータを一元管理・可視化するソフトウェアを導入することで、リアルタイムでデータを共有できるネットワークを構築することが可能になります。
5 サプライチェーンのDXに役立つツール・サービスの具体例
サプライチェーンにDXを導入する際、具体的にどのようなツールやサービスが求められるのでしょうか。特に有効なのは以下の3つです。
- ERPシステム
- RPAツール
- BPSP
それぞれの特徴を以下に詳しく解説します。
5-1 ERPシステム
ERPシステムは、サプライチェーンのDXを推進するうえで重要なツールの一つとして注目されています。
ERPは「Enterprise Resource Planning:企業資源計画」の略で、企業の資源(ヒト・モノ・カネ)を管理・計画することを指します。製造・配送・販売・会計・人事といった業務管理の各プロセスのデータを一元管理できるITツールが、ERPシステムです。ERPシステムを導入することによって、サプライチェーン全体の各ステークホルダー間でリアルタイムに情報共有が可能になり、業務効率化や意思決定の迅速化につながることが期待されています。また、サプライチェーンマネジメントをサポートする基幹業務との連携が強化されるため、業務効率の改善も目指せます。
現在はさまざまなERPシステムがクラウドサービスとして提供されており、一からシステムを構築しなくても導入ができるため、比較的短期間での導入が可能です。
5-2 RPAツール
RPAツールも、サプライチェーンマネジメントのさまざまな場面で活用できる有効なツールの一つです。
RPAとは「ロボティック・プロセス・オートメーション」のことで、人間が行っていた業務を自動化する技術を指します。特に、パソコン上での操作や事務作業など、ホワイトカラー職の業務を自動化するために広く利用されています。サプライチェーンの業務では、受発注処理・在庫管理・請求処理などの定型業務をRPAツールで自動化することで、業務効率の向上が期待できます。
また、手作業による処理を減らすことで、人件費削減や、人的ミスの防止にもつながります。
現在、さまざまなRPAツールが提供されており、各企業のニーズに応じたツールを選択することで、短期間での導入が可能です。
5-3 BPSP
BPSPは、サプライチェーンマネジメントにおける「決済」の業務に導入できるサービスです。
BPSPとは「Business Payment Solution Provider」の略で、企業間の決済を代行する仕組みのことを指します。BPSPを利用することで、例えば請求書払いしか受け付けていないサプライヤーや外注先などに対しても、クレジットカード決済が可能になります。また、BPSPを活用すれば、決済をオンラインで完結できるため、決済業務のペーパーレス化・デジタル化が進み、業務の効率化にもつながります。
6 サプライチェーンのDXはデジタル化から始める
サプライチェーンのDXとは、デジタル技術を活用して業務プロセス・ビジネスモデルを大きく変革することです。ただし、単にアナログの業務をデジタル化するだけではDXは完了しませんが、DXへ向けた第一歩としてデジタル化は不可欠な要素となります。サプライチェーンのDXを実現するために、本コラムでご紹介したさまざまな施策やテクノロジー導入のニーズが増していくことが予想されます。
TISでは、DXのニーズに応えるサービス・ビジネスを展開する企業様に向けて、企業間取引における決済のデジタル化・DXにつながるソリューションを提供しています。また、サービスの実現に向けて、事業検討の段階から伴走支援を行っています。
DX支援のサービス展開を検討している企業様は、ぜひTISへご相談ください。
【企業間取引 関連記事はこちら】
●中小企業に求められるデジタル化。中小企業を支援するサービス検討に向けたヒントとは?
●BPSPとは?導入メリットや請求書支払い代行サービスの仕組みを解説