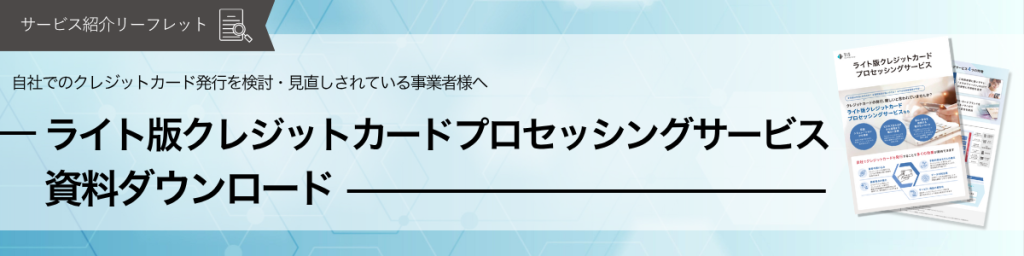Z世代は1990年代後半から2010年代初頭に生まれた世代で、インターネットやSNSと共に育った「デジタルネイティブ」として知られています。この世代は、オンラインツールを日常的に活用しながら、新しい消費行動を生み出していることが特徴です。本記事では、Z世代の特徴や消費行動を掘り下げながら、企業が成功するためのマーケティング戦略を解説します。
1 Z世代とは?X、Y世代との違い、世代別の特徴
2 Z世代の消費行動の特徴とその影響
2-1 オンラインショッピングの普及とZ世代のデジタル消費
2-2 「モノ」から「コト」へ、体験重視の消費行動「エモ消費」
3 Z世代とSNSの深い関係
3-1 SNSがZ世代の消費行動に与える影響
3-2 SNSを活用したマーケティング戦略の重要性
4 Z世代に響くマーケティング戦略のポイント
4-1 パーソナライズされたサービスや商品がZ世代に与える影響
4-2 企業の透明性と社会的責任がZ世代の消費志向に影響
5 Z世代向けマーケティング成功事例
5-1 成功事例①:サステナブルブランドの取り組み
5-2 成功事例②:コラボレーションや限定商品戦略
5-3 成功事例③:推し活×クレジットカードで新しい金融体験
6 Z世代に向けた企業のアプローチ方法
6-1 Z世代をターゲットにした商品開発のヒント
6-2 デジタル広告とSNSを活用した効果的な戦略
7 調査結果では2030年以降はZ世代が社会の中心に
8 まとめ
1 Z世代とは?X、Y世代との違い、世代別の特徴
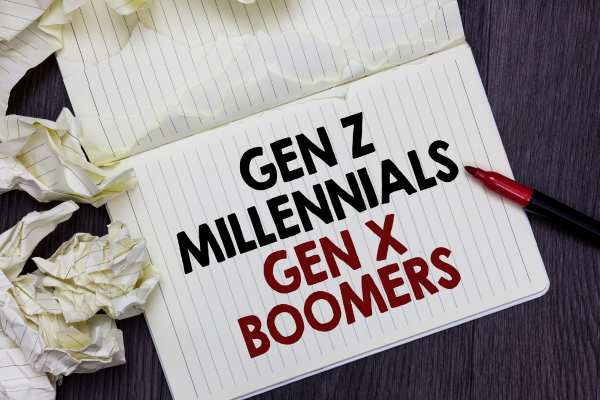
Z世代とは、1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代を言い、X世代、Y世代に続く世代です。スマートフォンとSNSの普及と共に育ってきた世代でもあり「デジタルネイティブ」「ソーシャルネイティブ」とも呼ばれています。また、オンラインでの情報収集・判断するスキルが高く、環境問題や社会的課題への関心が強いことが特徴です。経済的には、安定志向で効率を重視し、自分の価値観に合うブランドや商品を選ぶ傾向があります。
X、Y、Z世代の年齢層と時代の背景は以下の通りです。
安定志向で、テレビや新聞などのマスメディアに慣れ親しんだ世代。
ミレニアル世代とも呼ばれ、義務教育では「ゆとり教育」が実施された世代も含む。インターネットの普及期に成長し、デジタル技術に対応してきた世代。
完全なデジタルネイティブとして育ち、スマートフォンなどのデジタルデバイスとインターネット環境が身近にあることが当たり前の世代
Z世代はITバブルの崩壊をはじめリーマンショックや東日本大震災、新型コロナウイルスの影響など、経済や社会が不安定な時代で育ってきたこともあり、将来に対して不安を抱えている人が多いとも言われています。そのため、保険や資産運用への関心が高く、年金や介護など将来の社会課題について考えている人も少なくないこともZ世代の特徴です。
さらに、2010年代後半生まれの世代は「α世代」と呼ばれています。
2 Z世代の消費行動の特徴とその影響

Z世代の消費行動は、デジタル技術を活用した「オンラインファースト」と、体験重視の「エモ消費」という独自の傾向があり、注目されています。Z世代の消費行動について詳しく解説します。
2-1 オンラインショッピングの普及とZ世代のデジタル消費
Z世代は幼少期からスマートフォンやSNSが身近な環境で育ち、オンラインショッピングも生活の一部となっています。そのため、Z世代の消費はスマートフォンを中心に展開され、モバイルファーストの傾向が見られます。
Z世代の特徴として保守的な価値観があり、消費行動に関しても「失敗したくない」「後悔したくない」という思いが強いことが特徴です。そのため、オンラインショッピングの際には購入前にSNSで商品情報を収集し、レビューや口コミを重視する傾向があります。特に、InstagramやTikTok、YouTubeなどのソーシャルコマースがZ世代の購買意欲に大きな影響を与えているため、企業はこれを踏まえた戦略が求められるでしょう。近年ではSNSで多くのフォロワーを獲得している「インフルエンサー」を広告に起用する戦略が急増しています。
2-2 「モノ」から「コト」へ、体験重視の消費行動「エモ消費」
Z世代は、物質的な商品よりも、体験に価値を見いだす「エモ消費」の傾向が強くなっています。「エモい」は、「emotional(感情的な)」から派生した若者言葉として知られ、エモ消費は共感したり感情を揺さぶられたりするような体験を目的とした消費行動を指します。エモ消費には「共感」「ハッピー(ポジティブな感情)」「シェア(共有)」の3つの要素が含まれると言われています。
例えば、旅行やフェス、イベントなどの体験型消費はZ世代に人気が高く、これらの体験を通じて得た思い出や写真をSNSで発信し、多くの人に共有することも「エモ消費」の一環といえるでしょう。
Z世代向けの商品やサービスの開発では、体験を意識することが重要です。また、ブランディングでは、ストーリーを持たせて消費者の感情に訴えかける「ストーリーテリング」も効果的でしょう。
また、定額制のサブスクリプションサービスは音楽や映画、ファッションなど幅広い分野で人気があります。
3 Z世代とSNSの深い関係

SNSはZ世代の日常生活に深く根付いており、消費行動にも大きな影響を与えています。特にSNSを活用したマーケティングが、企業にとって重要な戦略といえるでしょう。
3-1 SNSがZ世代の消費行動に与える影響
TikTokやInstagram、YouTubeといったプラットフォームは、Z世代の購入意欲に大きな影響を与えています。特にショート動画は、15秒以内で商品の魅力をわかりやすく簡潔に伝える手段として効果的です。また、フォロワー数が多いインフルエンサーの影響力は大きく、彼らが商品を紹介・推奨するプロモーションは高い購入率を生み出します。
さらに、Z世代はSNSで商品の情報や口コミ・レビューを検索し購入するかどうかを判断する傾向にあるため、SNSを通じてZ世代の興味を引くことがマーケティングの大きなポイントといえるでしょう。
3-2 SNSを活用したマーケティング戦略の重要性
SNSを使ったマーケティングでは、視覚的なインパクトが特に重要です。高品質な画像や動画、ストーリーテリングを駆使したコンテンツは、Z世代の心を掴むためには欠かせません。また、プラットフォームごとに適した戦略を立てることも大きなポイントです。Instagramではビジュアル重視、TikTokではエンターテインメント性のある動画が購買意欲を刺激します。
そして、SNSでプロモーションを行う時にはSNS広告のターゲティング機能を活用し、ターゲットにピンポイントで訴求することも重要な戦略の一つです。
4 Z世代に響くマーケティング戦略のポイント

Z世代に向けたマーケティングを成功させるには、彼らの価値観に寄り添った戦略が必要です。特にパーソナライズや企業の透明性が重要なポイントとなります。
4-1 パーソナライズされたサービスや商品がZ世代に与える影響
個性を重視するZ世代は「自分らしさ」を表現できる商品・サービスを求める傾向があります。カスタマイズが可能な商品や、個人の好みに合わせたサブスクリプションサービスが人気です。例えばシューズや時計など、自分で色・デザインを選べる製品は、企業が提供するユニークな体験として話題を集めました。
また、DIYイベントやものづくり体験など、完成までの過程を楽しめる体験型のサービスもZ世代には人気です。自分でデザインを考え自分の手で作り上げていく体験は、エモ消費を好むZ世代と親和性が高いと言えます。
4-2 企業の透明性と社会的責任がZ世代の消費志向に影響
Z世代は「エシカル消費」を好む傾向にあります。エシカル消費は社会課題への取り組みを応援する購買行動を指し、サステナビリティ(持続可能性)や企業の社会的責任(CSR)への意識が高いことが特徴です。例えば環境に優しい素材を使った製品やフェアトレード商品を扱う企業、サプライチェーンの透明性が高い企業は高い信頼を得られるでしょう。
近年では「サステナブルファッション」「エシカルファッション」などの言葉も広く使われるようになり、多くのアパレルブランドも意欲的に取り組んでいます。
5 Z世代向けマーケティング成功事例
次に、Z世代に向けたマーケティングの成功事例を紹介します。各事例のポイントや手法を分析し、効果的なアプローチ方法を考えましょう。
5-1 成功事例①:サステナブルブランドの取り組み
エコフレンドリーな素材を使ったアウトドアアパレルブランド「パタゴニア」は、環境問題に対して積極的な姿勢を打ち出し、Z世代からの支持を集めています。同社は、製品自体の魅力だけでなく、「製品を修理して長く使う」カルチャーを提案し、持続可能性を訴求したことで、ブランドロイヤルティを確立しました。
具体的なポイントは以下の通りです。
5-2 成功事例②:コラボレーションや限定商品戦略
スポーツブランド「ナイキ」は、人気アーティストやデザイナーとのコラボ商品を展開し、Z世代の心を掴んでいます。例えば、「トラヴィス・スコット」とコラボレーションした限定スニーカーは発売直後に完売するなど、大きな話題を集めました。これは、Z世代の消費心理における「限定性」への強い関心を利用した事例の一つです。さらに、発売前には「ティザー動画」やSNSを活用して情報を小出しにし、好奇心を刺激。Z世代に人気のあるインフルエンサー・アーティストとのコラボレーションを展開し、ブランドの認知度向上に貢献しました。
5-3 成功事例③:推し活×クレジットカードで新しい金融体験
フィンテック企業「ナッジ株式会社」は、未来の金融体験を創出するクレジットカードとして「Nudge(ナッジ)カード」を発行しています。Nudgeカードの大きな特徴は、ファンカードとしての楽しさ(クラブ機能)を備えていることです。カード利用者は、さまざまなクリエイターやスポーツチーム、ショップ・サービス、自治体など、多彩なジャンルの「クラブ」と提携したカードを選べます。そして、カードを使うことでクラブの支援となり、利用者はオリジナル画像や動画の特典が受けられる仕組みです。
普段のキャッシュレス決済が「推し活」になることや、専用アプリで簡単に申し込み・操作できることがZ世代に注目され、Nudgeカードの利用額のうち7割以上を10代・20代が占めるサービスとなりました。環境保護や海外支援、動物愛護をテーマとしたソーシャルグッドのジャンルも展開し、エシカル消費に関心のあるZ世代の心をつかむマーケティング戦略を実施しています。
6 Z世代に向けた企業のアプローチ方法
Z世代へ効果的なマーケティングを行うには、商品開発と広告戦略を組み合わせ、彼らの価値観に寄り添ったアプローチがカギとなります。
6-1 Z世代をターゲットにした商品開発のヒント
Z世代が求めるのは、トレンドを取り入れつつも持続可能性を意識した商品です。例えば、再利用可能な素材を使ったファッションアイテムや、個性を表現できるカスタマイズ商品が支持されています。先述の通り、Z世代はサステナビリティ(持続可能性)や企業の社会的責任(CSR)への関心が高いため、サプライチェーンの透明性や企業理念を明確に伝えることが重要です。
また、商品の背景や製造過程のストーリーを打ち出し、共感や感動を促す「ストーリーテリング」を活用するアプローチも効果が期待できます。
6-2 デジタル広告とSNSを活用した効果的な戦略
Z世代に響くアプローチとして、ターゲティング広告やインフルエンサーを起用したプロモーションが効果的です。特にSNSのプラットフォームを活用し、UGC(一般ユーザーが作成したコンテンツ)でレビューや感想を投稿してもらうことで、リアルな体験を共有できるでしょう。また、TikTokのショート動画広告やInstagramのリール広告・ストーリーズ広告など、各プラットフォームの特性を活かしたアプローチも注目されています。
7 調査結果では2030年以降はZ世代が社会の中心に

日本において、Z世代は2030年には総人口の約3割、2050年には約半数を占め、主要な購買層として消費トレンドを牽引するようになると予測されています。今後は、エシカル消費や体験型消費がさらに拡大し、VRやARなどの技術を活用した新たな消費体験が普及するかもしれません。また、AIや新技術によりパーソナライズされた広告やサービスがさらに進化し、Z世代の消費体験をより豊かにすることも期待されます。
企業は、これらのトレンドを見据えた長期的な戦略を構築することが重要です。
8 まとめ
Z世代の消費行動を理解することは、現代のマーケティング戦略において欠かせません。デジタルネイティブ世代であるZ世代の心を掴むには、体験型消費や企業の透明性、サステナビリティを重視し、SNSを活用した戦略を展開することが効果的でしょう。
将来的に、主要な購買層の半数を占めると言われるZ世代ですが、時代の変化と共に消費行動も進化し、多様化する可能性があります。
TISはデジタルネイティブ世代が使いやすいスマホファーストなクレジットカードを実現する「ライト版クレジットカードプロセッシングサービス」を提供しています。
ライト版クレジットカードプロセッシングサービスは、Z世代の消費行動の特徴を踏まえ、ユーザーのニーズに応じた機能に絞り込むことで、最短6ヶ月でのサービス導入を実現しました。導入コスト・期間を削減しつつ、新たなターゲットユーザーの獲得が期待できます。
サービスの詳細や活用方法について、お気軽にお問い合わせください。
【クレジットカードプロセッシングサービス関連記事はこちら】
●クレジットカードのイシュアとは?意味や役割、アクワイアラの違いを分かりやすく解説
※この記事が参考になった!面白かった! と思った方は是非「シェア」ボタンを押してください。