OMO:Online Merges with Offlineの略で、オンラインとオフラインを統合するマーケティング手法のひとつ。オンライン(ECサイト)とオフライン(店舗)を一体として捉え、ユーザー体験の最適化を重視する概念を指す。
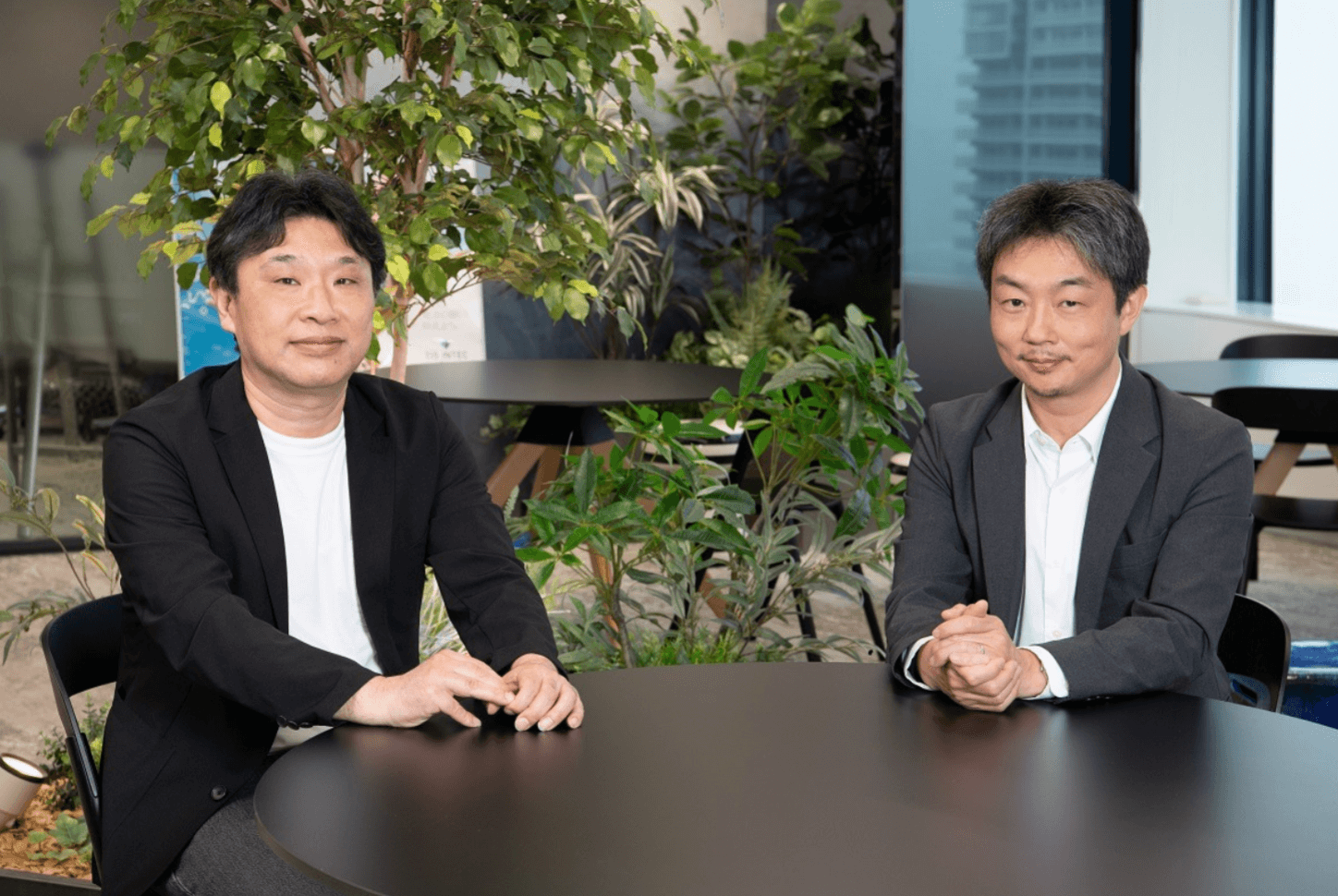
今回は、ソフトバンクグループの決済サービスプロバイダー(以下、PSP)としてECサイトや店舗にさまざまな決済⼿段を提供するSBペイメントサービス株式会社の小笠原氏をお招きして、PSPの視点から、OMOの重要性についてお伺いしました。本コラムでは、小売業における消費者行動の変化とそれに伴うOMOへのニーズを掘り下げていきます。
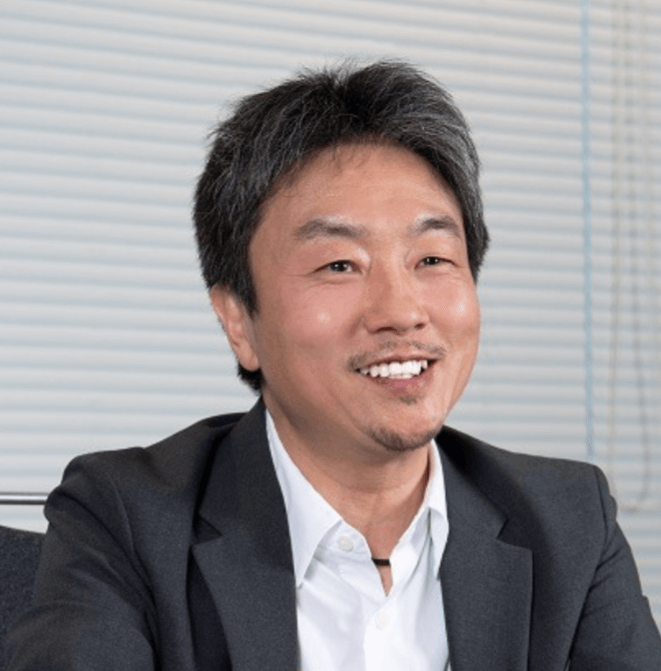
SBペイメントサービス株式会社
プロダクト開発本部 サービス企画部 部長
小笠原 通孝氏
2007年、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(現SBペイメントサービス株式会社)入社。料金収納業務やシステム構築を経験した後、決済代行サービスのオペレーション企画にて大手加盟店の決済導入・オペレーション構築を担当。さらに、同社企画部門にてオンライン決済サービスの拡充や決済端末・サービスの開発、国内・海外送金サービス開発に従事。

TIS株式会社
デジタルイノベーション事業本部
DIコンサルティング&プログラム企画部 エキスパート
鈴木 剛
1996年、株式会社東邦銀行入社。預金/為替、窓口、融資を経験。2002年、ソフトバンクファイナンス株式会社(現SBIHD)入社。決済代行サービスの営業、企画を担当。その後、同グループの住信SBIネット銀行株式会社で営業/企画を経験。2008年、楽天グループ株式会社入社。楽天初の外部ECサイトへのサービスに従事。2016年、株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ(現パーソルP&T)入社。タブレットPOSに関連した金融サービスを企画、アライアンスを担当。2022年、TIS株式会社入社。決済関連ビジネスに従事。
1.PSPとして利便性と快適性の高い決済を提供する、SBペイメントサービス
-SBペイメントサービスが決済代行サービスを事業化した背景
2.変わる消費者の購買行動、コンシューマー向け決済で求められること
-消費者の購買行動の変化
-コンシューマー向け決済のニーズ
3.消費者行動の変化と決済のデジタル化で、OMOの需要が高まっている
-SBペイメントサービスがOMO事業に参入する背景
-OMO事業参入の課題
4.OMOにおいては現金の流れとPOSデータが重要
-OMOにおけるPOSシステムの活用
5.PSPは決済のUIを提供するけれど、そのサービスの本質はUXにある
-OMO事業の本質
6.OMOの変化についていくこと、先を見越すことが、PSPとして重要
-SBペイメントサービスが見る今後の対面決済の動向
7.まとめ
1.PSPとして利便性と快適性の高い決済を提供する、SBペイメントサービス
-SBペイメントサービスが決済代行サービスを事業化した背景
鈴木
本日はよろしくお願いいたします。
今回はPSPを最前線で牽引する小笠原氏に、消費者行動の変化、それに伴うOMOへのニーズについてお話を伺いたいと思います。でははじめに、貴社が決済代行サービスを事業化した背景を教えていただけますか。
小笠原
SBペイメントサービスは、ソフトバンクグループの一員として決済ソリューションを提供する企業です。
ソフトバンクグループには、「情報革命で人々を幸せに」という理念があり、弊社は利便性と快適性の高い決済サービスによって人と人との価値を結び付け、より良い社会の実現に貢献したいという考えのもとに立ち上げられました。SBペイメントサービスの中心となる事業は「オンライン決済サービス」と「店舗向け決済サービス」ですが、それ以外にも「支払代行サービス」や「バーチャルカードの発行」など決済周辺のサービスを幅広く展開しています。
オンライン決済では、ECサイトやオンラインサービス向けにさまざまな決済手段を提供してきました。デジタルコンテンツやショッピングなどの購入代金を、月々の携帯電話料金とまとめて支払うことができる「ソフトバンクまとめて支払い」などのキャリア決済も、これにあたります。また、店舗向け決済では、小売店や飲食店などに対してキャッシュレス決済を提供しています。
鈴木
素晴らしい理念ですね。店舗向けのキャッシュレス決済では、TISとも協業いただいておりますね。
小笠原
TISさんには、SBペイメントサービスの店舗向けキャッシュレス決済において補完的な役割をお願いしています。お店のキャッシュレス化の推進や、キャッシュレスニーズへの対応、特にQRコード決済の提供についてご協力いただいています。また、弊社では決済端末にさまざまなアプリケーションを搭載することができますが、TISさんと日本カードネットワークさんとの合弁会社であるtance社が提供するアプリと、SBペイメントサービスが提供するアプリが相互利用できるようになっており、両社のサービスの足りない部分を補いつつ、協業させていただいています。
2.変わる消費者の購買行動、コンシューマー向け決済で求められること
-消費者の購買行動の変化
鈴木
貴社が小売店や飲食店にQRコード決済の提供を始めたのはいつからでしょうか。
小笠原
私はオンライン決済がまだ普及していない2007年にSBペイメントサービスに入社したのですが、当時のキャッシュレス決済はクレジットカード決済が主流で、QRコード決済も存在しませんでした。日本におけるQRコード決済の本格的な普及は2018年頃からと言われていますので、2019年頃にQRコード決済の提供を開始した弊社は、かなり早い段階からQRコード決済に取り組んできたと言えます。当時はQRコード決済を提供する事業者はほとんどなく、QRコード決済のプラットフォームを持つTISさんにご協力いただきながらのスタートでした。
鈴木
オンライン決済の普及に当初から携わってきた貴社は、この数年の消費者の購買行動の変化をどのように見ていらっしゃいますか。
小笠原
オンライン、オフラインの視点から見れば、消費者の購買行動は変わってきていると思います。今まではECサイトと店舗で分かれていた”買い物”も、「店舗(オフライン)で実物を見てから、ECサイト(オンライン)で安く購入する」こともあれば、逆に「ECサイトで商品を比較検討して、店舗で商品を確認して購入する」こともあります。消費者の購買行動ではオンラインとオフラインの融合が進み、お店はECサイトと店舗を一体として捉えなければならない時期にきていると思います。
オムニチャネルやOMOの話題は以前から取り沙汰されていましたが、もうOMOに取り組まないと店舗が生き残れないところに小売業界自体が来ているのだと思います。
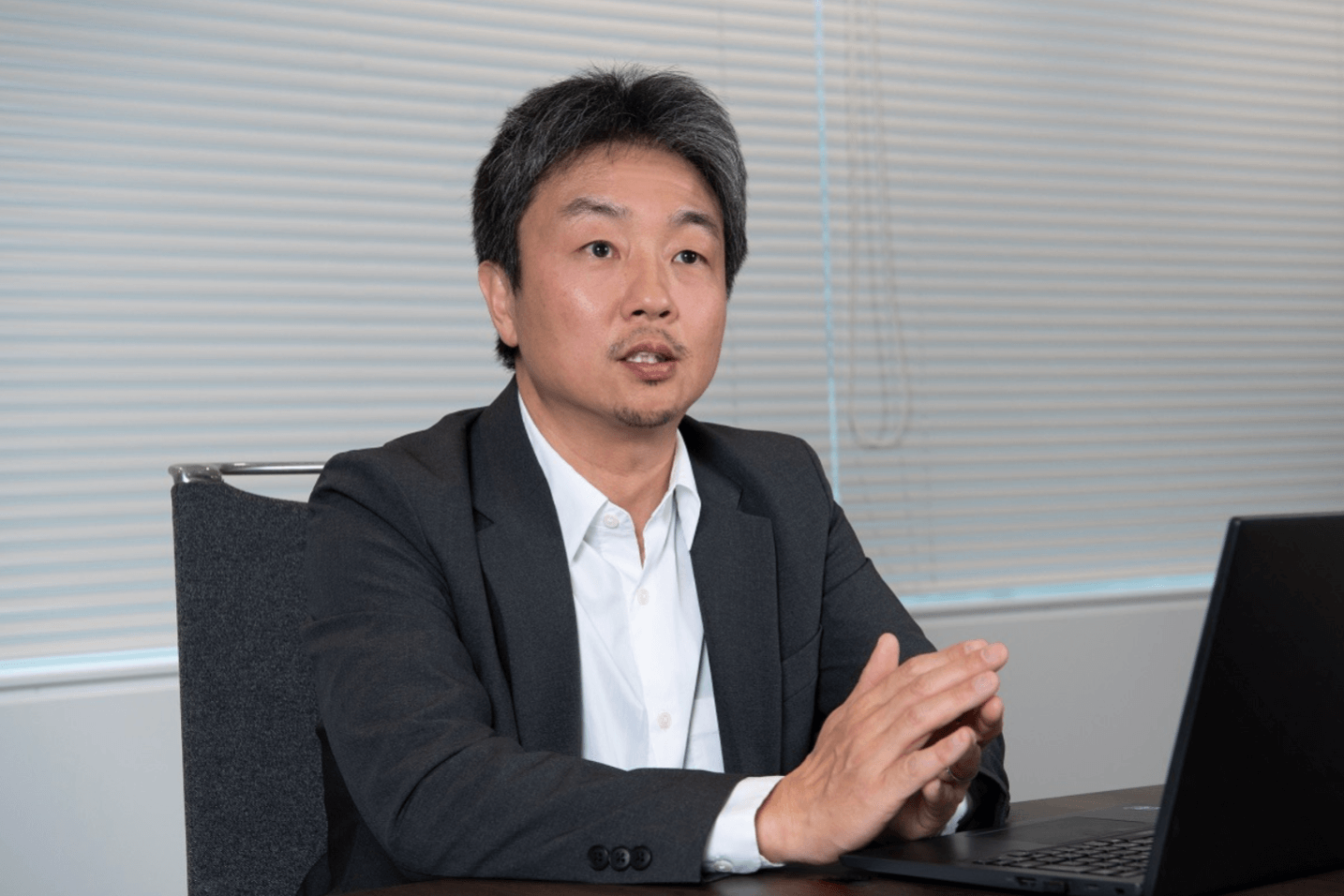
-コンシューマー向け決済のニーズ
鈴木
OMOの視点から、今の消費者から何を求められていると思いますか。
小笠原
これはなかなか難しい質問ですが、シームレスな決済に対するニーズは高いと考えています。コンシューマー向け決済では、とにかく”簡単に買える”ことが重要になるでしょう。例えば、ワンクリックで買える、顔認証で買える、そうした”簡単に買える”ためのUI/UXを消費者に提供していく必要があると思っています。実際に「ソフトバンクまとめて支払い」などのキャリア決済は、IDやパスワードの入力だけで簡単に利用できることで若者を中心に人気があります。
こうした”簡単に買える”決済のインターフェースとして、スマートフォンは非常に優れています。スーパーで商品をカートに入れ、レジを通さずに決済を行うことや、レストランで食事をしてテーブルで支払いを済ませることも、スマートフォンで可能になります。今後の店舗決済では、スマートフォンをどのように活用していくかも重要になります。
一方で、Alipay+(アリペイプラス)のような海外の決済手段のニーズも高まっています。海外の方が日本に来て買い物をする時や、日本のECモールで買い物をする時に、自分がいつも使っている決済手段をそのまま利用できれば、それも”簡単に買える”と言えるでしょう。
3.消費者行動の変化と決済のデジタル化で、OMOの需要が高まっている
-SBペイメントサービスがOMO事業に参入する背景
鈴木
SBペイメントサービスさんはどのような経緯でOMO事業に参入されるのでしょうか。
小笠原
弊社がOMO事業に参入する理由としては、消費者行動の変化と店舗におけるOMO需要の高まりが挙げられます。そして、ソフトバンクグループ全体の戦略にも合致していました。もともとソフトバンクグループでは「Beyond Carrier(ビヨンドキャリア)」という、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的に事業を展開する成長戦略を掲げており、通信事業を通じてスマートフォンやモバイルインターネットの普及を進めています。
鈴木
具体的にはどのようなサービスを提供していくのでしょうか。
小笠原
私どもの提供する決済端末は、アプリでさまざまな機能を追加していけることが強みです。これを利用して、ソフトバンクグループ全体として店舗や消費者に「決済+αの価値」を提供することがひとつの目標になります。具体的には、決済端末を通じて得られたデータの活用支援などを考えています。
PSPとして決済手段だけを提供するのではなく、お店のサポート、例えばAIによるお客様の来店予測などデジタルマーケティングの総合支援といったものも含めて提供し、「決済+αの価値」をグループ全体で創出していきたいという思いが強くあります。

OMO事業参入の課題
鈴木
OMO事業への参入にはどのような課題があると思いますか。
小笠原
やはり多数の店舗を抱える大型商業施設と少数店舗で展開する小売店では、決済手段や決済端末に求められているニーズがそれぞれ違いますので、それぞれに対してサービスをどう最適化していくのかは、なかなか難しい課題だと思います。
例えば、スマートフォンやタブレットを決済端末として活用するサービスがありますが、配送業者にとって社用の携帯電話がそのまま決済端末として使えることは、とても便利です。しかし配送先でそれが壊れてしまうと、代替手段がなく、決済ができなくなってしまう。だから配送業向けの決済端末は壊れないことが一番のニーズです。保険などの訪問販売では、商品説明のためにスマートフォンやタブレットの画面が大きいことが求められます。業種や業態により求められるニーズも違いますので、どう最適化していくかが私たちの課題です。
ニーズの違いは決済端末に搭載するアプリケーションでも対応しています。現在流通している決済端末の多くは、日本語しか表示されません。たくさんの国の方々が訪れる観光地のお店や旅館、コンビニで、それぞれの国の言語の数だけ決済端末を用意するのは無理があります。たくさんの国の言葉に対応したいというニーズには、1台の決済端末のアプリケーションで複数の言語に切り替えられることでお応えしています。
4.OMOにおいては現金の流れとPOSデータが重要
-OMOにおけるPOSシステムの活用
鈴木
グループに携帯キャリアを持つことは、顧客一人ひとりの属性や嗜好、購買や行動履歴などに基づいて、最適な情報やサービスを提供するパーソナライズドマーケティングにおいて大きなアドバンテージだと思いますが、OMOでは他に何が重要でしょうか。
小笠原
そうですね。マーケティングという視点では、キャッシュレス決済の情報だけでなく、現金の流れを把握することも重要です。POSでキャッシュレス決済データと現金決済データを一元的に把握することができれば、来店予測やキャンペーンに利用し、OMOとして顧客に新たな価値を提供することができるようになります。また、POSのデータを分析することでキャッシュフローの改善提案にも繋げていけると思います。売上から投資するのではなく、売上を予測して先に投資できれば、繁忙期に向けて必要な人材や商品を十分に確保でき、より売上に貢献できるかもしれません。
しかし、大型商業施設やコンビニなどでは自社システムと連動したPOSが導入されていますが、少数店舗
を展開する小売事業者では、POSの導入はまだまだ進んでいません。これは導入コストの問題もありますが、PSPがPOSの有用性を店舗に伝えきれていないとも感じています。
5.PSPは決済のUIを提供するけれど、そのサービスの本質はUXにある
-OMO事業の本質
小笠原
決済は商品とお金を交換する手段で、キャッシュレス決済はその価値交換のコストや工数を削減することはできますが、新しい決済手段の導入だけで売上が伸びるわけではありません。
もちろん、お客様が使いたい決済手段が使えることや、「超PayPay祭」のようなポイント還元キャンペーンが集客につながることもありますが、売上向上を図るには、決済を通じてどのような購買体験をお客様に提供できるかが重要です。優れたUIを提供することも大事ですが、私どもはOMO事業の本質はUXにあると考えています。
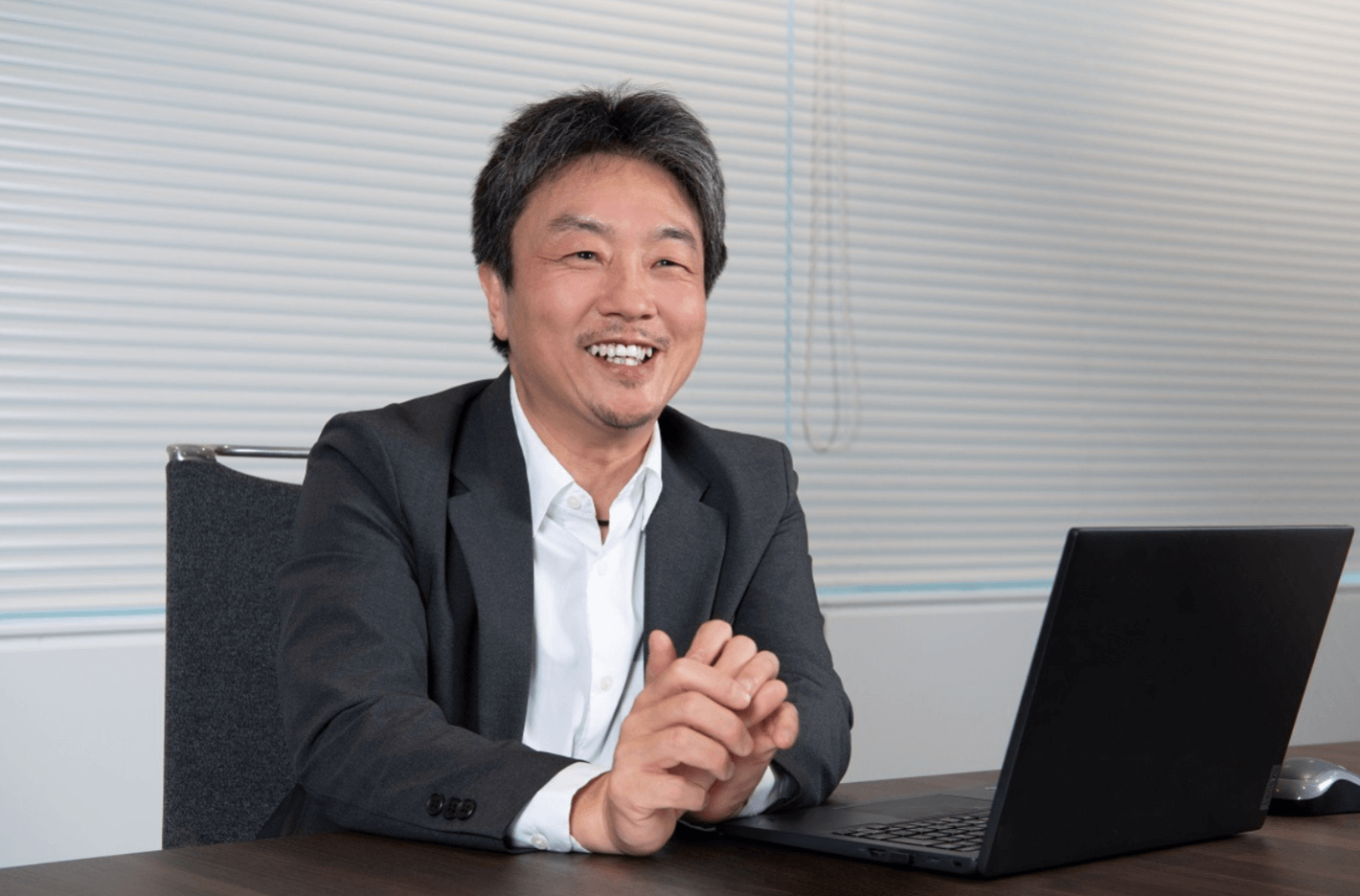
小笠原
対面決済では、決済は購買行動のフロントで、実はその後ろにある多くの要素が重要です。スマートフォンが決済端末として優れたUIであることは間違いなく、OMOでもさまざまな可能性があります。
このUIに「決済+α」のアプリケーションを搭載して、「決済という手段」を通して顧客にどんな体験を提供し、店舗の課題をどう解決していくのかがPSPに問われてくると思います。私たちのビジネスは「UIを提供するけれど、そのサービスの本質はUXにある」と言えるでしょう。こうした提案はTISさんも得意分野ですよね(笑)
6.OMOの変化についていくこと、先を見越すことが、PSPとして重要
-SBペイメントサービスが見る今後の対面決済の動向
鈴木
対面決済のニーズは今後どうなると思いますか。
小笠原
私は対面決済の利用シーンをどう増やしていくかに注目しています。QRコード決済の多様化とポイント付与キャンペーンによる利用促進で、QRコード決済は一定の普及を果たしたと考えており、ここから次の新しい対面決済が登場して広がることはもう難しいのではないかと思っています。今後は決済の統合が始まり、決済に+αの価値を付けるフェーズに移るのではないでしょうか。
極端な話、将来的には決済にスマートフォンなどの端末が不要になる可能性もあると思っています。
鈴木
決済に+αの価値が求められるようになると、SBペイメントサービスさんの収益構造も変わってくるのでしょうか。今は決済手数料が収益の柱になっていると思いますが、そこに先ほどのマーケティングサービスなどが加わってくる可能性はありますか。
小笠原
まさにその通りだと思っています。トランザクションデータの提供をはじめ、決済に関するあらゆるデータが収益となる可能性があります。海外のPSPの収益構造を見ると、決済と決済以外の収益がすでに半々となっている事業者が多く見られます。日本のPSPの場合は、まだ決済手数料収益の比率が非常に高いのですが、今後は決済手数料以外の収益の獲得にシフトしていくと思います。そのためには、SBペイメントサービスとしても店舗に対して決済以外のメリットを提供していかなければいけないと思います。
決済端末やPOSから得られる購買データを使い、AIで購買データを分析することで、”いつ何を売るといいですよ”とか、”こういう商品を仕入れておくべきです”といった予測も可能になるでしょう。店舗は仕入れのリスクを減らすことができ、飲食店では廃棄ロスも減らせます。アルバイトを雇用するタイミングやシフトなども、予測に従いどんどん自動化されていくと思います。
OMOを取り巻く変化についていくこと、決済のこれからを予測することは、PSPにとってとても重要です。SBペイメントサービスもOMO事業に参入する以上、「決済に+αの価値」を積極的に提供していきたいと思います。
7.まとめ
✓SBペイメントサービスは、国内を代表するPSPとして、オンライン決済から店舗向け決済
まで、利便性と快適性の高い決済サービスを提供している
✓オンライン(ECモール)とオフライン(店舗)が融合する消費者の購買行動の変化により、OMOの重要性
は増し、小売業はOMOに取り組まないと生き残れない状況になりつつある
✓OMOやコンシューマー向け決済においてUI/UXはとても重要で、「簡単に行えること」を追求した新た
なUI/UXの施策が求められている
✓OMOやPOSを通じたトランザクションデータの収集や、AIのデータマーケティングへの活用が進み、
小売業はより利便性、快適性の高い決済サービスを提供することが可能
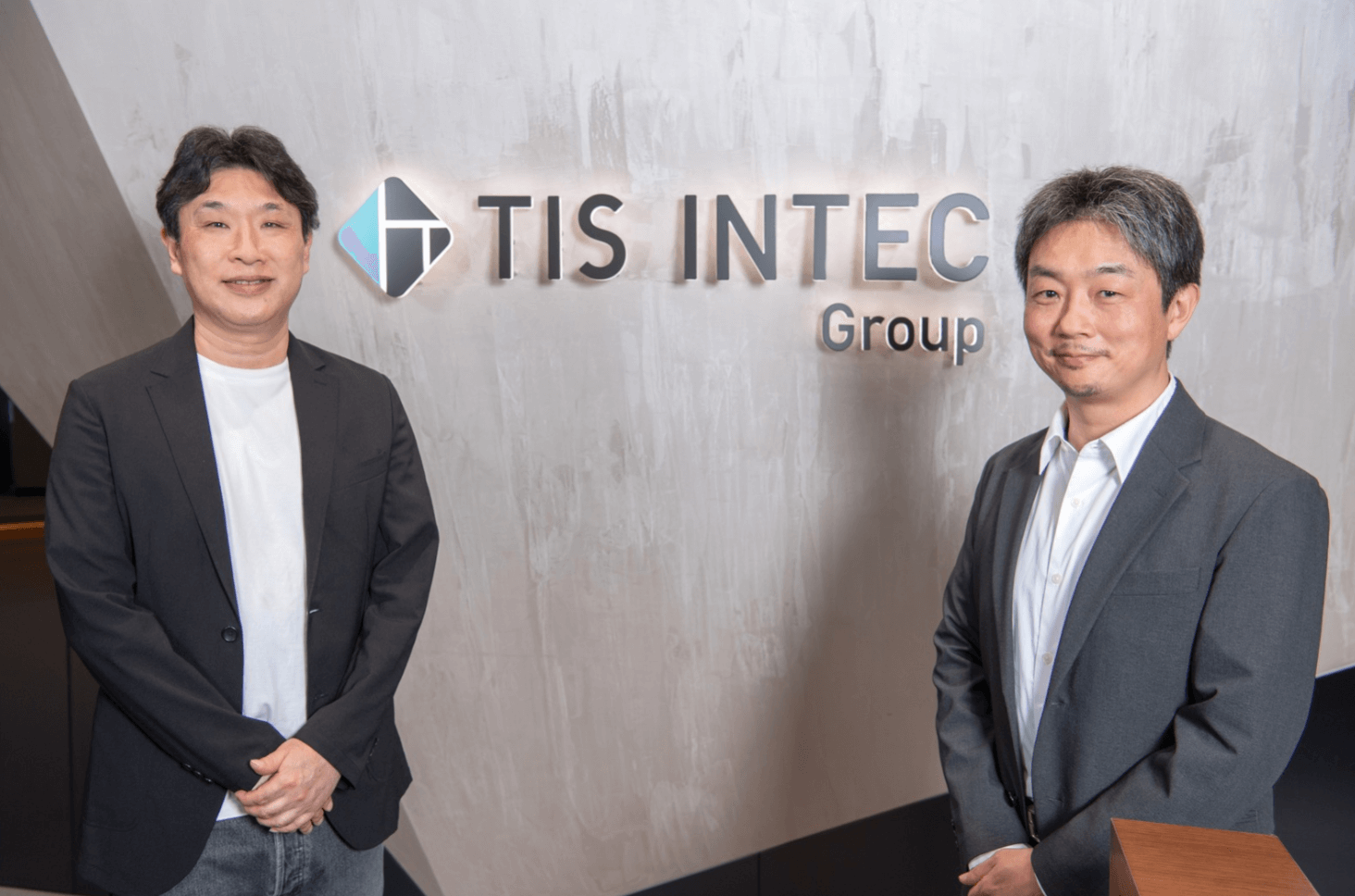
取材日:2025年3月12日
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です
▼その他、関連取材記事はコチラから
第1回:奥谷孝司氏が語る「小売業のDX化」デジタルを武器に顧客体験を高める方法とは?
第2回:POS+(ポスタス)代表本田氏が語る「POSサービス」の視点で考える店舗のDX化
第3回:デジタルガレージ社の戦略から見る、対面決済と企業間取引(BtoB取引)決済の現状と今後の展望
第4回:ビジネスコンサルタントの視点から見る、ウォレットサービス参入に必要な”価値の提供”とその波及効果
※この記事が参考になった!面白かった! と思った方は是非「シェア」ボタンを押してください。
