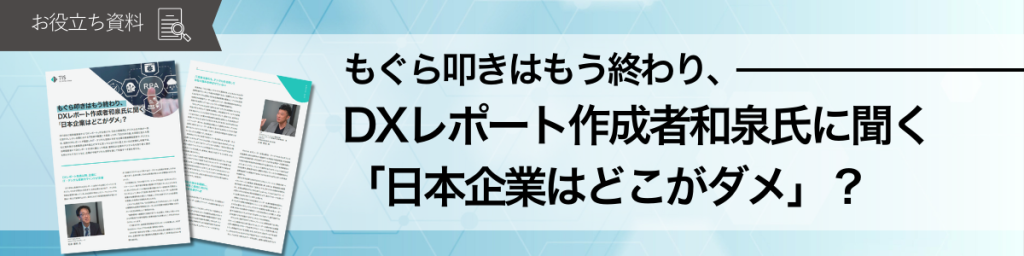中小企業では、IT人材の不足や資金不足といった課題により、デジタル化の進展が遅れている現状があります。そのため、限られたリソースの中で適切な施策を厳選し、効率的にデジタル化を進めることが重要になります。また、必要に応じて外部リソースを活用することも有効な手段のひとつです。
本コラムでは、中小企業がデジタル化をどのように進めれば良いのか、基本的な3つの施策と、デジタル化を検討すべき主な業務分野について解説します。さらに、中小企業のデジタル化を支援するサービスを検討している事業者に向けて、事業創出のヒントもご紹介します。
1 中小企業がデジタル化を進める必要性
1-1 システムの老朽化に対応するため
1-2 人材不足の問題を解消するため
1-3 競争力を向上させるため
2 調査データから分かる中小企業のデジタル化の現状と進まない理由・課題
3 中小企業がデジタル化を進めるためにできる3つの施策
3-1 デジタルデバイスの導入
3-2 クラウド型ツールの導入
3-3 オンラインサービスの利用
4 中小企業がデジタル化を検討したい業務分野の例
4-1 勤怠管理
4-2 マーケティング活動
4-3 契約業務
4-4 請求・決済業務
5 中小企業のデジタル化ニーズが高まっている
1 中小企業がデジタル化を進める必要性
「デジタル化」というと、大企業にとって重要な取り組みというイメージを持つかもしれません。しかし近年、中小企業においてもデジタル化の必要性が高まっています。その背景には、主に3つの理由があります。
- システムの老朽化に対応するため
- 人材不足の問題を解消するため
- 競争力を向上させるため
それぞれ詳しく解説します。
1-1 システムの老朽化に対応するため
中小企業のデジタル化が必要な理由の1つは「システムの老朽化」に対応するためです。2018年に経済産業省が発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』では、老朽化した「レガシーシステム」の保守・運用に多くの人的コストがかかっていることが問題視されました。レガシーシステムは、IT技術の変化に伴ってカスタマイズを繰り返し、その結果、システムが複雑化し、保守・運用にかかるコストが増大する傾向にあります。
デジタル化を進めることで、こうしたレガシーシステムから脱却することが可能になります。例えば、従来のシステムを外部のソリューションに置き換えることで、保守・運用にかかる人件費やコストの削減が期待できます。
1-2 人材不足の問題を解消するため
デジタル化は「人材不足の問題」の解消のためにも必要だといえます。中小企業にとって、労働人口の減少による人材不足は深刻な問題です。日本では少子化などの影響もあり、必要な人材を確保することが年々難しくなっています。このような状況の中で、デジタル化による業務効率化を進めることで、「少人数でも業務を円滑に運営できる体制」を構築することが求められています。
1-3 競争力を向上させるため
中小企業が「競争力を向上させる」ためにも、デジタル化は不可欠な要素となっています。現在のビジネス環境は「VUCA」とも呼ばれる変化の激しい時代に突入しています。VUCAとは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の4つの頭文字から来る言葉です。このような、「予測が難しい時代」において、迅速な意思決定や柔軟な対応力が求められます。
デジタル化を進めることで、コスト削減や業務の迅速化を実現し、市場の変化にも柔軟に対応できる社内体制を構築できます。これにより、企業としての競争力を維持・向上させることが一層期待できるでしょう。
2 調査データから分かる中小企業のデジタル化の現状と進まない理由・課題
中小企業のデジタル化の現状や課題について、中小企業基盤整備機構が実施した「中小企業の DX 推進に関する調査(2023 年)」を参考に確認しておきましょう。
まず、デジタル化の現状についてですが、同調査の「DX の取組状況について」のアンケートでは、「必要だと思うが取組めていない」および「取組む予定はない」という回答が合計で68.8%に達し、半数以上の中小企業がデジタル化やDXに取り組めていないことが分かります。
デジタル化の取り組みが進まない理由・課題として、同調査の「DX に取り組むに当たっての課題について」の回答で多く挙げられていたのは以下の3つです。
- ITに関わる人材が足りない: 28.1%
- DX推進に関わる人材が足りない: 27.2%
- 予算の確保が難しい: 24.9%
この調査結果から、特に「人材不足」が原因でデジタル化・DXが進んでいないことが明らかになりました。デジタル化を促進するためには、まずデジタル化を推進する担当者を確保することが重要です。中小企業向けのコンサルティングサービスを活用し、専門家のサポートを受けながらデジタル化の計画を進めるといった対策も有効でしょう。
3 中小企業がデジタル化を進めるためにできる3つの施策
中小企業のデジタル化を進めるためには、どのような施策を進めていけば良いのでしょうか。中小企業でも取り組みやすい施策として以下の3つが挙げられます。
- デジタルデバイスの導入
- クラウド型ツールの導入
- オンラインサービスの利用
それぞれについて以下で詳しく解説します。
3-1 デジタルデバイスの導入
デジタルデバイスの導入は、デジタル化の基本ともいえる施策です。例えば、持ち運びがしやすいスマートフォン・タブレットなどのモバイルデバイスは、外出先での情報共有やリアルタイムなデータ管理に役立ちます。ノートPCと異なり、直感的な操作が可能なため、紙の資料・帳票をデジタル化する際にも有効です。
さらに、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)の技術が普及により、モバイルデバイスだけなく、さまざまな製品をインターネットに接続して管理することが可能になっています。
3-2 クラウド型ツールの導入
クラウド型のツールは、中小企業にとって導入しやすいソリューションです。自社でサーバーを設置したり、PCにソフトウェアをインストールしたりする必要がなく、インターネットに接続するだけで、すぐに利用を開始できるという手軽さが魅力です。例えば、「クラウドストレージ」を活用することで、社内のデータをオンライン上で保存・共有できるようになります。これにより、外出先・自宅からもアクセスでき、業務の柔軟性が向上します。
また、業務効率化に役立つクラウド型ツールには「勤怠管理システム」「MAツール」「オンライン決済システム」などがあります。企業ごとに最適なツールを導入することで、業務のデジタル化が進み、業務効率の向上が期待できます。
3-3 オンラインサービスの利用
オンラインで利用できる代行サービスなどを活用することも有効な施策のひとつです。Web経由でアウトソーシングすることで、自社でデジタル環境を構築せずに、デジタル化を推進することができます。例えば、「請求書支払い代行サービス」を利用すれば、紙の請求書を使用した業務をオンラインで外注でき、請求処理のペーパーレス化や業務負担の軽減が可能になります。
また、ITツールではなく、人の手によるサービスであっても、「オンラインで利用できるサービス」であれば、業務のデジタル化に貢献するといえます。こうしたオンラインサービスを活用することで、業務の効率化を図りながら、企業の生産性向上にもつなげることができます。
4 中小企業がデジタル化を検討したい業務分野の例
中小企業では、具体的にどのような業務分野をデジタル化できるのでしょうか。特にデジタル化を実践しやすい分野として以下の4つが挙げられます。
- 勤怠管理
- マーケティング活動
- 契約業務
- 請求・決済業務
それぞれどのようにデジタル化できるのか、以下に詳しく解説します。
4-1 勤怠管理
中小企業がデジタル化しやすい業務分野のひとつが「勤怠管理」です。例えば「勤怠管理システム」を導入することで、勤怠管理を簡単にデジタル化できます。勤怠管理システムとは、打刻によるデータを集計して従業員の労働状況を把握し、賃金計算などを自動化できるツールです。オンラインでも打刻できるタイプもあり、リモートワークの勤怠管理にも活用できます。
また、タイムカードなどを使用したアナログな勤怠管理をデジタル化することで、作業の効率化や正確なデータ管理が可能になります。さらに、法改正に対応した勤怠管理システムを導入することで、労務のコンプライアンス遵守にもつながります。
4-2 マーケティング活動
マーケティングの業務も、デジタル化しやすい業務分野のひとつです。例えばMA(マーケティング・オートメーション)などのデジタルツールを使うことで、宣伝・マーケティング活動の効率化が可能になります。MAとは、メール・SNS・広告などのマーケティング施策を自動化し、見込み顧客や既存顧客のデータを一元管理できるツールです。
MAの導入によって、メルマガ配信やSNSの運用、広告の管理など、手作業で行っていた作業の自動化ができます。また、従来人が行っていた営業活動の一部を、Web広告などのデジタル施策に置き換えることで、業務負担を軽減することもできます。デジタル化を進めることで、マーケティング施策のデータを蓄積しやすくなり、効果測定や改善がしやすくなるため、PDCAを素早く回し、効率的に売上向上を目指すことが可能になります。
さらに、近年では生成AIを活用したSEO記事の作成や広告文案の作成なども進んでおり、より精度の高いマーケティング戦略を実施できるようになっています。
4-3 契約業務
契約業務も、便利なデジタル化ツールが多く提供されており、比較的導入しやすい分野です。例えば、「電子契約システム」を導入することで、契約書の作成や管理をデジタル化し、オンライン上で契約締結を完了させることが可能になります。これにより、リモート環境でも契約業務をスムーズに行うことができ、業務の効率化につながります。
また、「契約書管理システム」を活用すれば、契約書の検索や更新管理が容易になり、紙の契約書よりも効率的な管理が可能になります。契約書をデジタル化することで、契約更新の期限管理を自動化できるほか、情報検索性が向上し、契約関連のトラブルを未然に防ぐことができます。
4-4 請求・支払い業務
請求書発行や決済業務も、デジタル化によって大幅に効率化できる分野のひとつです。例えば、「オンライン決済システム」を導入することで、企業間取引やECサイト向けのオ決済をンライン上完結できるようになります。オンライン決済を導入することで、請求書の発行や振込確認の手間を削減でき、決済業務のペーパーレス化・キャッシュレス化を実現できます。
TISではオンライン決済システムの導入サポートを提供しています。請求から会計・決済を一気通貫で行えるソリューション開発の支援も行っています。また、中小企業を顧客とする大手企業向け決済ソリューションもご提案できます。
5 中小企業のデジタル化ニーズが高まっている
中小企業におけるデジタル化にはさまざまな手段がありますが、近年、取引環境の構築や業務の効率化といった課題に対応するニーズが高まっています。特に、請求・税務・契約・決済などの取引フローにおいて、依然として紙ベースの作業や手作業での入力が主流となっており、多くの中小企業でデジタル化が進んでいないのが現状です。
TISでは、こうしたニーズに応えるため、企業のバックオフィス業務のDX化に取り組んでいます。具体的には、請求書管理・入出金管理など各企業が異なるクラウドサービスを利用している経理業務全体をデジタル化するためのソリューションを提供しています。
また、各社が導入しているクラウドサービスと会計システムをプラットフォーム上で連携させることで、1つのプラットフォーム上で経理業務のDXを実現できる仕組みを構築しています。
さらに、企業間取引における新市場を狙う企業向けに、新たな金融サービスの提供や自社サービスの高度化を支援しています。具体的には、「自社サービスへの金融機能の組込み」や「金融機能の内製化」といった幅広いニーズに対応可能です。
中小企業を顧客に持つ企業様で、受発注から決済までの業務を一貫して提供するトータルサービスを構築したいとお考えの際には、ぜひTISへご相談ください。
PAYCIERGEへのお問い合わせ【企業間取引 関連記事はこちら】
●BPSPとは?導入メリットや請求書支払い代行サービスの仕組みを解説