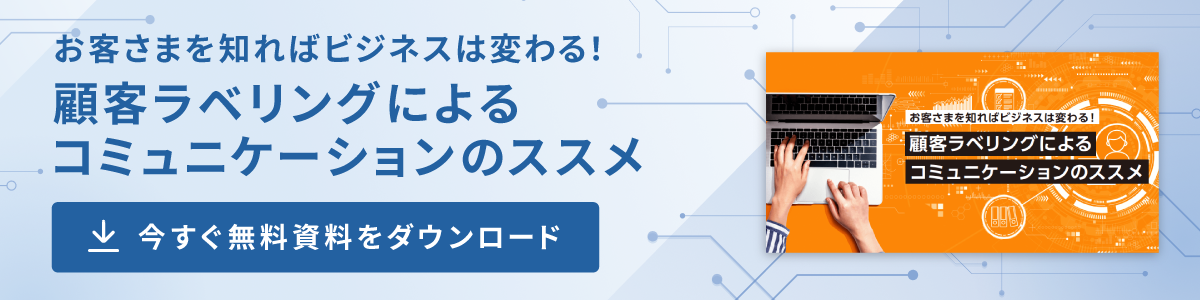デジタル技術の進化により、多くの企業がマーケティング戦略の立案や商品やサービスの開発・改善のために顧客データの分析を行っています。精度の高い分析システムを構築し、データを活かした意思決定を行うことは、現代のビジネスにおいて不可欠な取り組みといえるでしょう。
本記事では、顧客データ分析を行う重要性やメリット、具体的な分析手法や、実際の企業の成功事例について解説します。
1 顧客データ分析とは
1-1 顧客データ分析の目的について
1-1-1 マーケティング施策の最適化
1-1-2 商品・サービス開発への活用
2 顧客データ分析によるメリットとは
2-1 顧客理解の深化
2-2 マーケティング戦略の最適化
2-3 商品・サービス開発への活用
3 分析する顧客データの種類
3-1 定量分析について
3-2 定性分析について
4 顧客データ分析の手法とは
4-1 RFM分析
4-2 行動トレンド分析
4-3 セグメンテーション分析
4-4 バスケット分析
4-5 デシル分析
5 顧客データ分析の注意点
5-1 分析目的の明確化
5-2 定量・定性データの併用
5-3 データの統合と整備
5-4 適切なデータ分析ツールの選定
6 顧客データ分析の事例
7 まとめ
1 顧客データ分析とは
顧客データ分析とは、自社の顧客データを集計して考察を行い、顧客についての理解を深めることです。
分析する顧客データには、年齢層・性別などの基本的な属性情報に加え、商品の購入履歴やWebサイトへのアクセス履歴、メールの開封履歴などの行動データも含まれます。オフラインの購買データを含む実店舗の情報も統合すれば、より立体的な分析が可能になります。
顧客に関する多角的なデータを集計して分析することで、自社の顧客の全体像や傾向を詳しく把握でき、マーケティングや商品企画などに活用できます。
1-1 顧客データ分析の目的について
目的については大きく2点あります。
1-1-1 マーケティング施策の最適化
顧客一人ひとりのニーズや嗜好、ロイヤリティのレベル(例:優良顧客/休眠顧客など)を把握することで、顧客行動に基づいた施策の「パーソナライズ」が可能になります。例えば、メール配信の文面やWebサイトに表示する内容を顧客ごとに最適化することで、反応率や購入率の向上が期待できます。
1-1-2 商品・サービス開発への活
顧客データを分析することで、これまで見えていなかったニーズを発見できることもあります。これにより、新商品の企画や既存サービスの改善へとつなげることが可能です。事実、多くの企業がこうしたデータに基づくインサイトを基に、ヒット商品やサービスを生み出しています。
2 顧客データ分析によるメリットとは
顧客データの分析は、企業活動全体の質を高めるための重要な基盤です。具体的には、以下の3つの観点から大きなメリットが期待されます。
- 顧客理解の深化
- マーケティング戦略の最適化
- 商品・サービス開発への活用
それぞれ以下に詳しく解説します。
2-1 顧客理解の深化
顧客データを分析することで、自社の顧客像をより立体的に把握できるようになります。
年齢・性別・居住地などの基本属性によるセグメンテーションに加え、購買履歴やWeb上の行動データを掛け合わせて分析することで、「売上に寄与している主要な顧客層」「ロイヤリティの高い顧客の特徴」といった傾向を可視化できます。
こうした理解を基に、顧客ニーズを的確に捉えた施策の立案が可能になります。
データを単なる数値で終わらせず、ビジネスの意思決定にどう活かすかが重要です。
2-2 マーケティング戦略の最適化
顧客データ分析は、直感や経験に頼ったマーケティングから脱却し、客観的なデータに基づく施策の立案を可能にします。
例えば、「自社製品は主に女性が購入しているはず」といった仮説が、実際のデータによって裏付けられるか、あるいは新たなインサイトが得られるかを検証できます。
さらに、行動履歴や嗜好に応じて異なるコンテンツを配信する「パーソナライズ」施策も、顧客データに基づいて実現可能です。これにより、より精緻なターゲティングや訴求ができ、顧客体験の向上や成果の最大化につながります。
2-3 商品・サービス開発への活用
顧客データ分析の結果は、商品・サービスの改善や新規開発にも大きく貢献します。
購入履歴や属性ごとの傾向を分析することで、「どの顧客層が何を求めているのか」「購入動機や離脱の理由は何か」といった洞察が得られます。特 に、アンケートやインタビューなどの定性的データと組み合わせることで、より深いインサイトを導き出すことが可能になります。
こうした分析を継続的に行うことで、既存サービスのブラッシュアップはもちろん、新たな価値提案につながる開発のヒントも得やすくなります。
3 分析する顧客データの種類
顧客データ分析において取り扱うデータは、大きく以下の2種類に分類されます。
- 定量データ
- 定性データ
顧客データ分析は上記2つのデータを組み合わせて行うのが一般的です。それぞれの違いや分析方法について、以下で詳しく解説します。
3-1 定量分析について
定量データとは、数値として計測・集計できるデータのことです。例えば、顧客の「年齢・性別・購入回数・時間帯・地域」などのデータが該当します。
このようなデータは、顧客の行動や傾向を数値的に客観把握できる点が特徴です。また、グラフやチャートなどを用いた視覚的な分析にも適しています。
なお、「顧客満足度」など、一見主観的な項目でも数値化して集計されている場合は、定量データとして扱われる点に注意が必要です。
定量データの分析には、CRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールといったシステムの活用が一般的です。
3-2 定性分析について
定性データとは、数値では表せない言語的・感覚的な情報を指します。
例えば、商品やサービスについての「使ってみた感想」「印象」「選んだ理由」など、数値ではなくテキスト などで表現されるデータが該当します。
定性データは、個々の顧客の主観的な声や感情を含むため、定量データほどの客観性・再現性はありません。しかしながら、顧客の「なぜ」に迫る深い洞察が得られる点が大きな強みです。
主な取得手段としては、自由記述式のアンケートやインタビュー、SNS上の投稿分析などがあります。
定量データと定性データはそれぞれ異なる特徴を持っていますが、両者を組み合わせて活用することで、顧客理解を多角的・総合的に深めることが可能になります。
4 顧客データ分析の手法とは
顧客データ分析には多くの手法がありますが、まず押さえておきたい基本的な分析アプローチは以下の5つです。
- RFM分析
- 行動トレンド分析
- セグメンテーション分析
- バスケット分析
- デシル分析
それぞれの特徴・分析方法を以下に解説します。
4-1 RFM分析
RFM分析とは「最終購入日:Recency」「購入頻度:Frequency」「購入金額:Monetary」の3つの指標を基に顧客を分類・評価する手法です。
RFM分析では、下図のように3つの軸で作成したグラフを基準として顧客を分類(セグメント分け)することで分析を行います。
RFM分析を行う際には、下記3つのデータについて、それぞれ一定の基準で顧客にスコアを付与します。
- 最終購入日:顧客が最後に購入した日付(近いほど高いスコアを付与)
- 購入頻度:一定期間内に顧客が購入した回数(多いほど高いスコアを付与)
- 購入金額:顧客が購入した合計金額(高いほど高いスコアを付与)
スコアを基に、顧客を「優良顧客」「安定顧客」「休眠顧客」などのセグメントに分類します。
これにより、離反リスクの高い層へのリテンション施策や、優良顧客へのアップセル・ロイヤリティ強化など、目的別のアプローチが可能になります。
4-2 行動トレンド分析
行動トレンド分析とは、顧客のWebサイトやアプリ上での行動履歴、来店履歴、購入経路などの「行動データ」の推移を時系列で追い、傾向を分析する手法です。
例えば、年間の売上推移やアクセス傾向を分析することで、季節要因・イベント要因・キャンペーン効果などを把握できます。また、売上の変動に寄与している主な顧客層を特定することで、施策立案におけるヒントにもなります。
この手法を活用することで、「いつ・どの顧客層にアプローチすべきか」といった、タイミング戦略の精度向上にもつながります。
4-3 セグメンテーション分析
セグメンテーション分析は、「年齢・性別・ライフスタイル」などさまざまな指標を軸にして、顧客を分類する手法です。「クラスタ分析」とも呼ばれます。
セグメンテーション分析ではビジネス分野・業種ごとのニーズに合わせてさまざまな評価軸が使われます。評価軸は、大きく分けて以下の4つに分類することが可能です。
- 地理的変数(地域など)
- 人口動態変数(年齢・性別など)
- 心理的変数(ライフスタイル・性格など)
- 行動変数(購入履歴・アクセス履歴など)
分類する際に使う軸の組み合わせは、分析目的に合わせて自由に設定できます。自社の顧客データ分析に役立つ評価軸の組み合わせをいかに発見するかが、セグメンテーション分析の成功を左右するといえるでしょう。
前述のRFM分析は、評価軸として「最終購入日」「購入頻度」「購入金額」を使うセグメンテーション分析の一種と位置づけることができます。
4-4 バスケット分析
バスケット分析(マーケットバスケット分析)とは、「一緒に購入される商品」を特定し、顧客の購買行動・ニーズなどの把握に役立てる手法です。「アフィニティ分析」とも呼ばれます。
バスケット分析では、以下の指標を算出することで、関連性の高い商品の組み合わせを分析します。
| 指標名 | 意味 |
|---|---|
| 支持度 (同時購買率) |
商品A・商品Bが同時に購入される割合 (商品AとBの同時購入者数 ÷ 購入者全体数) |
| 信頼度 (指定商品同時購買率) |
商品Aを購入した顧客が商品Bを購入する割合 (商品AとBの同時購入者数 ÷ 商品Aの購入者数) |
| 期待信頼度 (関連商品購買率) |
商品Bが購入される割合 (商品Bの購入者数 ÷ 購入者全体数) |
| リフト値 | 商品A・商品Bの関連性の高さを示す指標 (信頼度 ÷ 期待信頼度) |
バスケット分析の結果は、実店舗での商品陳列を検討する際の参考として活用できます。またECにおいては、「この商品を購入した人はこちらも買っています」などのレコメンド商品を表示させる際の基準としても活用可能です。
バスケット分析を行うには、実店舗においてはデータ集計ができるPOSレジ、ECにおいてはCRMなどの集計ツールを導入して、顧客の購買履歴を収集する必要があります。
4-5 デシル分析
デシル分析とは、購入金額の累計金額が高い順に顧客を10段階のグループに分けて分析する手法です。
グループごとの売上構成比を可視化することで、「どの顧客層が売上に大きく貢献しているか」を明確にします。
例えば、上位2グループ(20%)の顧客が全体売上の80%を占めていた場合、パレートの法則(80:20の法則)が成立していることになります。
デシル分析で上位のグループに属する顧客に対して予算を多く投入して優先的にアプローチするといった、マーケティング施策における優先順位付けや予算配分の判断材料として活用されます。
デシル分析はシンプルな手法であり、エクセルなどの表計算ソフトでも簡単に実行することができます。
5 顧客データ分析の注意点
顧客データの分析を実行する際には、以下の点に注意することが大切です。
- 分析目的の明確化
- 定量・定性データの併用
- データの統合と整備
- 適切なデータ分析ツールの選定
それぞれ以下に詳しく解説します。
5-1 分析目的の明確化
顧客データを分析する際には、その「目的・目標」を明確にしておくことが大切です。
目的が不明確なまま分析を開始すると、施策に活かせないデータが蓄積されるだけになりかねません。顧客データを分析する目的を決めておくと、分析手法を選びやすくなります。
例えば、自社の商品やサービスに対する愛着・忠誠心の高い「ロイヤルカスタマー」を増やすことを目的とする場合には、「RFM分析」が効果的です。
他にも「メルマガの効果改善」「新商品の開発」「解約率を下げる」など、顧客データ分析にはさまざまな目的が考えられます。単に「自社の顧客の理解を深める」といった漠然とした目標ではなく、成果につながる具体的な目的を設定したうえで顧客データ分析を進めていきましょう。
5-2 定量・定性データの併用
顧客データ分析では、定量データ(数値)に偏ることなく、定性データ(主観・理由)も含めた総合的な分析が求められます。
例えば、定量データから自社の優良顧客に「20代の男性が多い」と分かっても、その理由までは定性データを組み合わせないと明らかになりません。
定量・定性データを組み合わせて分析することで、定量データの数値・グラフの結果に至る「理由」「原因」などを含め、深い顧客インサイトを得ることが可能になります。
保有するデータについて、定量・定性データの両方について必要なデータがそろっているか確認し、必要に応じて追加でアンケートを実施するなど、必要なデータを十分に集めることが大切です。
5-3 データの統合と整備
顧客データを複数チャネル(例:実店舗・EC・モバイルアプリ)で収集している場合は、データの統合と一元管理が必須です。
チャネルごとに個別で管理していると、同一顧客のデータが重複して記録されたり、行動パターンが断片的にしか把握できなかったりするリスクがあります。
CRMツールなどを活用し、顧客単位で統合されたデータベースを構築することが、正確な分析の土台となります。
なお、既に重複が発生している場合でも、多くのCRMシステムには自動重複検知・統合機能が搭載されており、データ整備作業の効率化が可能です。
5-4 適切なデータ分析ツールの選定
顧客データ分析を適切に行うには、自社のニーズに合致したツールの選定が不可欠です。
顧客データの分析に使われる代表的なツールの例としては以下の3つが挙げられます。
| ツールの種類 | 特徴 |
|---|---|
| CRM(顧客関係管理) | 既存顧客のデータを一元管理できるツール。顧客データを蓄積・数値化して分析するなどの機能がある。 |
| MA(マーケティングオートメーション) | マーケティング施策を自動化できるツール。顧客セグメントごとに異なるメールを自動配信するなど、データを活かした施策の実行が可能。 |
| SFA(営業支援システム) | 営業活動を効率化するツール。見込み顧客のデータ管理・分析などが可能。特にBtoB分野で導入されることが多い。 |
これらのツールには多様な製品が存在するため、自社の業種・事業規模・課題に応じて最適なものを選定することが、分析精度と業務効率の向上につながります。
6 顧客データ分析の事例
顧客データ分析を取り入れてマーケティング施策や業績向上につなげた、企業の成功事例を5社ご紹介します。
- 株式会社ファミリーマート
【イベントレポート】ファミマのデジタル新規事業|ProSharing Consulting - スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
会員数750万人の「スターバックス リワード」に学ぶ、ロイヤルティプログラムを通じたCX向上:MarkeZine - 株式会社アーバンリサーチ
新しい顧客像を発見し、顧客単価が約7,000円上昇!アーバンリサーチに学ぶデータマーケティングとは|MarkeZine - 合同会社ユー・エス・ジェイ
「データをゲストの体験にどう活かせるか?」─USJが目指す、“届けたい体験”から逆算するデジタル戦略 – XD(クロスディー) - 株式会社JTB
CVR45%増の事例も! JTBのDMPを用いたデータドリブン成功の秘訣|Web担当者Forum
7 まとめ
デジタルマーケティングが高度化する現在、顧客データ分析の精度を高める取り組みは、企業の競争力強化に直結する重要な要素となっています。
顧客データ分析を適切に実施するためには、基本的な手法の理解に加え、顧客データを効率的に収集・管理するためのシステムを構築する必要があります。目的を明確にし、定量・定性の両側面から多角的にデータを活用することで、より実効性のあるマーケティング施策や商品開発が可能になります。
顧客データ分析のためのシステム・インフラの構築・改善などをご検討の際には、TISにご相談ください。TISでは、スマホアプリによって顧客の行動を可視化するサービス「キャクシル」など、顧客データ分析のシステム構築を支援する幅広いサービスをご提供しています。顧客データ分析にまつわるご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
行動可視化サービス「キャクシル」についての詳しい資料はこちらからダウンロード頂けます。
【独自Pay関連記事はこちら】
●ロイヤルカスタマー戦略とは?成功のための手法や事例について解説
※この記事が参考になった!面白かった! と思った方は是非「シェア」ボタンを押してください。